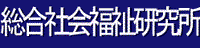
総合社会福祉研究所 > 福祉のひろば > 福祉のひろば目次71-75
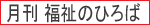
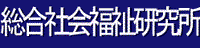
|
福祉のひろば目次71-75
総合社会福祉研究所 > 福祉のひろば > 福祉のひろば目次71-75 |
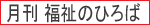
|
特集●民間社会福祉の危機と可能性
民間社会福祉の危機と可能性 石倉康次
特集1 当事者・住民のねがいとともに
ルポ・ケア付き仮設住宅を訪ねて-兵庫・芦屋 三好洋正
「このゆびと~まれ」はこんなところ 惣万佳代子・西村和美
地域活動が大きな力に-麦の子保育園のとりくみ 田部洋子
地域で暮らし働きつづけたい-さつき福祉会グループホームの五年間 小井田 史
特集2 民間社会福祉と公的責任
民間社会福祉の特性を生かした施設運営を-施設経営者の立場から 青木泰信
国民とあゆむ民間社会福祉を-労働組合の立場から 村木忠夫
社会福祉法人の自信・自戒・自覚-行政の立場から 富田眞一(板井史郎)
「徳風会」公金不正流用事件から-利用者・住民・労組の力で法人・施設の民主化を 水野洋次郎
資料 「これからの都道府県・指定都市社協のあり方に関する検討会」報告 資料
どうなる!? 年金大改悪 竹本光代
海外レポート 幕引きはまだ早い--ハンセン病患者・恢復者のワークショップに参加して 寺園敦史
テレビで出会った人びと
夢はでっかい「地球館」-中村幸昭さん(鳥羽水族館館長) 岡田良一
福祉にいきて 4ページの自分史
私たちが関わらなければ援助の手が届かないお年寄りはいっぱいいます-小林房子さん 岡崎艶子
「中途障害」を理由とした解雇は無効-関西電力を提訴した私 二見徳雄
神戸からのレポート
「公的支援を」の住民投票実施-賛成に84万票 編集部
知ってしまった以上、何かをしなくては-ボランティアとして、公務員として 北野敏子
地域から職場から
学生たちが作った社会福祉ガイドマップ 芝田英昭・磯 法子・加藤たみ子・問山あや・堀口香織
大阪での「介護一一〇番」活動がブックレットに 松村秀明
追悼・都築秀夫先生 富永隆治
◇
グラビア すばらしき仲間たち-和歌山・青年学級と共同作業所 宮脇 達
きり絵 大阪の橋29 加藤義明br>
児童文学と子ども像 戸佐陽子
いち、にのさん 高橋弘生・眞由美
老いのつぶやき、老いのこころ 大泉 勝
ボランティア活動の現場から16 登山を通して視覚障害者のノーマライゼーションを実践-徳本茂孝さん 岡崎艶子
著者に聞く 黒田 学
映画とにんげん 神谷雅子
古代史の旅 宇治田和生
演劇 関口晃宏
いらっしゃいませ! 取材協力 パレットひびき
福祉のあしあと 眞木和義
言葉のアルバム すみれ乳児保育園
時評 三浦タツ
特集●生活保障の最低基準を考える
現行社会福祉政策下で「最低基準」を問う意味 真田 是
ルポ・ミニ介護ホーム「宅老所よりあい」からみた最低基準 岡 幸江
在宅福祉の最低基準を問う-ホームヘルパー派遣訴訟から 青木佳史
文化としての豊かな「食」を 篠崎晴美
納得いかない生活保護施設の低水準 丸野ちづる
子どもの最善の利益守る最低基準に 高橋朝子
子ども・職員からゆとりを奪う現行基準 山本政幸
中途障害者の働く場をつくって 末永ひとみ
最低生活をとらえる視点 浜岡政好
社会保障構造改革とは何か 今井文夫
ルポ・低い年金基準に生活は苦しく 三好洋正
児童福祉法「改正」をどうみるか
「改正」児童福祉法の活用のポイントと課題 木下秀雄
学童保育を権利として確立させるために 前田美子
テレビで出会った人びと25
平和の願い込めた証言-渡辺和子さん 岡田良一
福祉に生きて 4ページの自分史
夢、実現! 母親たちの心意気の記念碑として誕生する「おひさま保育園」-勝部麗子さん 岡崎艶子
福祉・医療の原点と可能性を教えてくれる『海くんが笑った。』 石倉康次・西原由美・本田陽子
精神保健福祉施設「ハートピアきつれ川」の活動 村上 清
精神障害とともに生きる-発病後20年。いま作業所建設にとりくむ 幸田俊充
正当な医療行為に診療報酬の支払いは当然-京都民医連中央病院「不当減点復活訴訟」に画期的な勝利 桜本憲一郎
若い目、若い芽
中学生が福祉施設で総合体験学習 徳庄博美・日垣良太
◇
グラビア 沖縄-過去、現在、そして未来 宮脇 達br>
きり絵 大阪の橋29 加藤義明
児童文学と子ども像 戸佐陽子
いち、にのさん 高橋弘生・眞由美
老いのつぶやき、老いのこころ 大泉 勝
ボランティア活動の現場から17 施設の子にカットの”出前” 目立たず自然体でこれからも-今村伸子さん(美容室「まな美」経営) 岡崎艶子
著者に聞く『障害をもつ人たちの憲法学習』(かもがわ出版) 玉村公二彦
映画のなかの女性たち 神谷雅子
古代史の旅 宇治田和生
演劇 関口晃宏
いらっしゃいませ 喫茶「じゃらんじゃらん」 宮部信太郎
福祉のあしあと 眞木和義
言葉のアルバム すみれ乳児院
1998年初頭にあたって 国民に背を向ける政治から、国民本位の政治の実現へ 真田 是
特集●権利にめざめて動きだすとき
1 当事者が主体となって
産炭地に夢ひらく住民参加のまちづくり-住民と行政の協働で誇れるふるさとに 中島利男
委託反対から保育政策づくりへ--アイデアあふれる取り組みの中から 佐藤正弘
仮設住宅巡回相談が広げた自立への希望-孤独だった被災者が立ちあがるとき 大橋 豊
最低生活保障の確立を求めて立ちあがる当事者-全国ですすむ全生連の取り組み 正岡幸久
2 福祉労働者のかかわり方
主人公は私たち-「仲間の会」の活動と職員の役割・視点 海野 博
子どもたちに陽のあたる保育園を-マンション建設にストップをかけた父母、職員たち 石川幸枝
生存権保障を求める国民運動の課題と福祉労働者の役割 石倉康次
若い目、若い芽 新春座談会-社会福祉と青年の生き方 自立し、発信し、連帯して 家平 悟・・坂本孝美・鈴木悦子・山本智光
医療保障を守るために
健康保険法の改悪で奪われる受療権 高橋俊敬
医療と生活を壊す二交替勤務制 香月直之
学生無年金障害者に年金を-審査請求にむけ、シンポジウムを開催 鴨井慶雄
テレビで出会った人びと
生活にとけこむ陶作品-河合卯之助・紀親子(陶芸家) 岡田良一
福祉に生きて 4ページの自分史
法制化元年を迎え、課題山積の学童保育を前進させる、大きなチャンス!-松井信也さん
スポーツに魅せられて アーチェリーが教えてくれた、私にもできるということ 鈴木一二美
神戸からのレポート
ひとりの医師として震災に関わり、市長選挙をたたかって 大西和雄
介護保険のここが問題
「尊厳ある人生」からみた介護保険法とは-人生全体をとらえる介護モデルの構築を 住居広士・江原勝幸
介護保険で高齢者ホームヘルプ事業はどうなる? 小野寿彦
◇
グラビア おひさまはみんなの友だち-広島・なかよし保育園の子どもたち 宮脇 達
きり絵 大阪の橋29 加藤義明
児童文学と子ども像 戸佐陽子
いち、にのさん 高橋弘生・眞由美
老いのつぶやき、老いのこころ 大泉 勝
ボランティア活動の現場から
視覚障害者も一組合員として生協活動に幅広く参加できる運動を-林野信子さん 岡崎艶子
著者に聞く『女性化する福祉社会』(勁草書房刊) 杉本貴代栄
本の紹介
西村有史著『開業医が歩んだ長い道 エイズ患者診ます』(青木書店)
あおぞら財団『まちあるきマップ 西淀川フィールドミュージアム』 (財)公害地域再生センター(あおぞら財団)
曽根富美子著『いつくしみの視野 全盲ママの愛と感動の育児記録』(たまひよコミックス編集部)
いこいの村『人として 第三巻』 滝野 稔
映画のなかの女性たち 神谷雅子
古代史の旅 宇治田和生
演劇 関口晃宏
いらっしゃいませ!「ろーずまりー」
福祉のあしあと 眞木和義
言葉のアルバム 高鷲保育園
時評 三浦タツ
特集●いま、福祉の仕事は
父母・住民の保育要求に応えて-自治体リストラの中での公立保育所の取り組み 田中登志江
「心のいやし」は安らげる生活の中で-虐待等で傷ついた子どもたちに向きあって 置田 守
生活施設建設の夢を実現して-障害者も職員も主人公の豊かな暮らしを 高橋順子
人として生きる-私たちの結婚を応援してくれる職員たち 山口清臣
私たちにできることを問いながら-地域に根ざす高齢者施設と職員 陶山まさ子
利用者と従事者の共同で制度の再生を-社会福祉構造改革の下での生活保護の現場から 小林厚介
福祉市場化から国民の福祉を守るために 水野洋次郎
福祉労働をとおして社会福祉を発展させる-福祉職場で働く人へのメッセージ 真田 是
新連載 介護保険法を追う
公的介護保険制度の諸問題 岡崎祐司
資料 介護保健法案等に対する衆議院厚生委員会および参議院本会議での附帯決議
「社会福祉の基礎構造改革」で何がねらわれているか 石倉康次
資料 「社会福祉の基礎構造改革について(主要な論点)」
98年度社会保障関係予算をみる
国民生活を直撃する大幅な削減予算 堀 幾雄
母子家庭の生活はどうなるの!?-児童扶養手当見直しの問題点 渡辺照子
テレビで出会った人びと
いつまでも華のある女-ミヤコ蝶々さん 岡田良一
福祉に生きて 4ページの自分史
よく働き、よく闘い、よく学び、よく楽しみ、仲間と共に視覚障害者の”夜明け”をめざす-藤野高明さん(全日本視力障害者協会会長) 岡崎艶子
田沼裁判が問うもの-社会福祉とはなにか 上田誠吉
保母の「頸肩腕障害・腰痛は公務災害」の判決-健康対策推進の大きな武器に 堤 浩一郎
海外レポート 父親の育児参加を支援-スウェーデンにおける有給育児休暇の父親月制度 訓覇法子
若い目、若い芽
中学生が調査した町のバリアフリー 上田 学
神戸からのレポート
震災復興に柔軟・多様な援助を 加藤和彦
◇
グラビア 響けうたごえ 平和とともに-日本のうたごえ祭典50周年in OSAKA 宮脇 達
きり絵 大阪の橋30 大和橋 加藤義明
児童文学と子ども像 戸佐陽子
いち、にのさん 高橋弘生・眞由美
老いのつぶやき、老いのこころ 大泉 勝
ボランティア活動の現場から17 阪神大震災の避難所で衣服を縫う”お針箱行脚”-窪井紀子さん 岡崎艶子
著者に聞く『欠陥だらけの介護保険』(かもがわ出版刊) 伊藤周平
本の紹介
アトム共同保育所
駒どりの家運営委員会『「駒どりの家」物語』(兵庫部落問題研究所)
共同作業所全国連絡会編『みんなの共同作業所』(ぶどう社)
宮尾茂子著『がんを道連れに13年』(未來社)
映画のなかの女性たち 神谷雅子
古代史の旅 宇治田和生
演劇 関口晃宏
いらっしゃいませ!「コーヒー&ギャラリー ルツ」
福祉のあしあと 眞木和義
言葉のアルバム すみれ保育園
時評 三浦タツ
特集●障害をもつ人の権利と生活保障
ぼくらの青年学級-障害をもつ青年たちに教育・労働・リフレッシユの場を 前川尚子
福祉の谷間から- 「後天性若年知的障害者」になった妻とともに富田秀信
市民がつくる八尾の「障害者ブラン」-親が運動の中心になりながら 「市民の手で障害者プランをつくる会」事務局
市民がつくる広島の「障害者プラン」-自治体労働者の役割 平野由子
障害児者が健康で暮らし続けられるように-医療をはじめ、生活全般を支えるシステムの確立を 坂野幸江
就労の実態から生活保障を考える 柳原一徳
成年後見制度で尊蔵ある生活の支援を 青木佳史
今、「障害をもつ人の権利と生活保障」を考える視点 石倉康次
連載介護保険法を追う②
社会保障運動の焦点と介護保険施行に向けた課題 岡崎祐司
家族介護の悲劇はなくなるか-「介護の社会化」と公的介護保険 中井紀代子
児童福祉法改正以降の保育政策の動向と問題点 杉山隆一
移送サービスのプロ集囲をめざして-なごや・リフトタクシーの取り組み 加藤長浩
行政と企業の責任を問う薬害ヤコブ病裁判 中島晃
神戸からのレポート
命あるうちに恒久住宅と公的支援を! 安田秋成
女性と福祉
再出発した生野学園-民間シェルターの役割と課題 今市恵
列島レポート
福岡市での児童館要求運動(福岡) 西山健児
働きやすい職場をめざして(兵庫) 大屋町社協分会
テレビで出会った人ぴと29
アイバンクで再ぴ輝く人生を-ある受眼者のねがい 岡田良一
福祉に生きて 4ぺ-ジの自分史⑮
障害者運動を通して、社会を変えていくのは主権者である私たち庶民であることを実感-金沢 子さん 岡崎艶子
総合社会福祉研究所だより
大阪の橋・きりえ/加藤義明
児童文学と子ども像/加藤陽子
いち、にのさん/高橋弘生・眞由美
老いのつぷやき、老いのこころ/大泉勝
ボランティア活動の現場から/池内満明
著者に聞く/岸田孝史
本の紹介
映画の中の女性たち/神谷雅子
古代史の旅/宇治田和生
演劇/関口晃宏
いらっしやいませ!
福祉のあしあと
言葉のアルバム/ひむろこだま保育園
時評/三浦夕ツ
総合社会福祉研究所 |